���H��ʖ@�̈ꕔ����������@�����A�����P�X�N�U���Q�O���Ɍ��z����A�X���P�X���A
�P�N��A�Q�N��ƒi�K�I�Ɏ{�s����܂��B
���e�͈ȉ��̒ʂ�ł��B
�P�c�����E�댯�^�]�ґ�
�Q�c����^�]�ґ���
�R�c���]�ԗ��p�ґ�
�S�c��Q�Ҍy����
�������Q�P�N�U���P���Ɏ{�s
���Ƌ��̌��i���Ԃ̉����i����P�O�N�j
�����ᔽ�s�ׂŖƋ������������҂ɑ�����Ԃ�
�P�N�ȏ�T�N�ȉ��@���@�R�N�ȏ�P�O�N�ȉ��@�ɉ�������܂�
���V�T�Έȏ�̍���^�]�҂̖Ƌ��X�V���ɂ�����F�m�@�\�������`���t��
�V�T�Έȏ�̍���^�]�҂��^�]�Ƌ��̍X�V�������悤�Ƃ���ꍇ�A�X�V���Ԃ�����������O�A�U
�����ȓ��ɁA�L���́A���f�͓��̔F�m�@�\�Ɋւ��錟�����Ȃ���Ȃ�܂���B
�������ʂ����̊�ɊY�����鎞�́A�u�Վ��K�������v���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ�������
���B
������ҍu�K�̎�u���Ԃ̉���
����ҍu�K�̎�u���Ԃ��X�V���Ԗ�������
�@�R�����ȓ��@���@�U�����ȓ��@�ɉ�������܂�
�������Q�O�N�U���P���Ɏ{�s
�����o��Q�҉^�]�ҕW�����̕\���̋`���t��
���߂Œ�߂鎋�o��Q�����邱�Ƃ𗝗R�ɁA�Ƌ�������t����Ă���҂́A�����ԉ^�]���Ɏ��o��
�Q�ɂ�����W���\�����`���t�����܂��B
�����ʎ��]�Ԃ̕����ʍs�Ɋւ���K��
���]�Ԃ͎ԓ��ʍs�������ł����A�u���]�ԕ����ʍs�v�̕W��������Ƃ��ɉ����A
�E���]�Ԃɏ��P�R�Ζ����̎�����c���Ȃǖ@�߂Œ�߂�҂��^�]����Ƃ�
�E�ԓ����͌�ʂ̏���A���]�Ԃ̈��S���m�ۂ��邽�ߕ�����ʍs���邱�Ƃ���ނȂ��Ƃ�
�͕����ʍs���ł��邱�ƂƂȂ�܂��B
����ԗp�w�����b�g�Ɋւ���K��
�����E�c����ی삷��ӔC�̂���҂́A�P�R�Ζ����̎����A�c�������]�Ԃɏ�Ԃ�����Ƃ��́A��
�ԗp�w�����b�g�𒅗p������悤�w�߂Ȃ���Ȃ�܂���B
���㕔���ȃV�[�g�x���g�̒��p���`���t��
�㕔���Ȃ̏���ɂ��Ă��V�[�g�x���g���p���`���t������A���ׂĂ̍��Ȃ̏�����A�V�[�g�x��
�g��`���C���h�V�[�g�𒅗p���Ȃ���Ȃ�܂���B
�������P�X�N�X���P�X���Ɏ{�s
�������^�]�s�ׂ��s�����҂ɑ��锱���̋���
| �𐌂��^�] | �T�N�ȉ��̒��͂P�O�O���~�ȉ��̔��� |
| ���C�тщ^�] | �R�N�ȉ��̒��͂T�O���~�ȉ��̔��� |
| �������m���� | �R�N�ȉ��̒��͂T�O���~�ȉ��̔��� |
�������^�]�i�e�F�E�����j�s�ׂɑ��锱���K��̐V�ݓ�
�����^�]�����邨����̂���҂ɑ��A�ԗ����������A��ނ������A�����^�]������
�ԗ��ւ̗v���E�˗����Ă̓��悵���ꍇ�́A���L�̒ʂ蔱�����܂��B
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
�����̑�
�~��`���ᔽ�i�Ђ������j�c�P�O�N�ȉ��̒��͂P�O�O���~�ȉ��̔����ƂȂ�܂��B
���^�]�c�T�N�ȉ��̒��͂P�O�O���~�ȉ��̔����ƂȂ�܂��B
�^�]�Ƌ��ؒ`���̌������c�ᔽ�s�ׁA�܂��͌�ʎ��̂��N�������^�]�҂́A�x�@�������̉^�]
�҂ɉ^�]���p�������邱�Ƃ��ł��邩�ǂ������m�F���邽�ߕK�v������ƔF�߁A�����߂�ꂽ
�ꍇ�͒��Ȃ���Ȃ�܂���B�ᔽ����Δ����̑ΏۂƂȂ�܂��B
�@�����P�U�N�U���̓��H��ʖ@�̉����̃|�C���g�ł��B
�����P�U�N�P�P���{�s
���g�ѓd�b���̎g�p�Ɋւ��锱���̌�����
�@�����Ԃ⌴���@�t���]�Ԃ̑��s���ɁA�g�ѓd�b������Ŏ����āA�ʘb������A���[���̑���M��
�̂��߂ɉ摜�𒍎��������́A�T���~�ȉ��̔����̔����̑ΏۂƂȂ�܂��B
�̂��߂ɉ摜�𒍎��������́A�T���~�ȉ��̔����̔����̑ΏۂƂȂ�܂��B
�������^�]��
�@�������m�����ɑ��锱�����T���~�ȉ��̔��������R�O���~�ȉ��̔����Ɉ����グ���܂��B
���\������
�P�@�W�c�\���s���ɂ��ẮA���f��댯�ɑ������������Ȃ��ꍇ�ł��A��������A�Q�N�ȉ��̒�
�������T�O���~�ȉ��̔����̔����̑ΏۂƂȂ�܂��B
�������T�O���~�ȉ��̔����̔����̑ΏۂƂȂ�܂��B
�Q�@�����^�]���ɑ��锱�����V�݂���A�T���~�ȉ��̔����ƂȂ�܂��B
�R�@������s�������^�]�����҂ɑ��锱�����A�Q���~�ȉ��̔��������T���~�ȉ��̔����Ɉ�����
�����܂��B
�����܂��B
�����P�V�N�S���{�s
��������֎Ԃ̓�l���K���̌�����
�P�@�������H�ɂ������l���K���̌�����
�@����܂ō��������ԍ����y�ю����Ԑ�p���H�ł̎�����֎Ԃ̓�l���͑S�ʋ֎~�Ƃ���Ă���
�������A�N��Q�O�Έȏ��ŁA��֖Ƌ����Ă������Ԃ��R�N�ȏ��̕��ł���A�������H����
�̓�l��肪�ł����悤�ɂȂ�܂��B
�������A�N��Q�O�Έȏ��ŁA��֖Ƌ����Ă������Ԃ��R�N�ȏ��̕��ł���A�������H����
�̓�l��肪�ł����悤�ɂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������ւ̓�l���֎~
�Q�@��l���֎~�ᔽ�̔��������グ
�@�������H���ł͏�L�A��ʓ��ɂ����Ă͓�֖Ƌ����Ă������Ԃ��P�N�ȏ��ł��邱�Ƃ���l
���̏����ł����A����Ɉᔽ�����ꍇ�A�T���~�ȉ��̔��������P�O���~�ȉ��̔����Ɉ����グ��
��܂��B
���̏����ł����A����Ɉᔽ�����ꍇ�A�T���~�ȉ��̔��������P�O���~�ȉ��̔����Ɉ����グ��
��܂��B
�R�@���S�m�ۂ̂��߂̋K�萮��
�@�x�@���́A��֎Ԃ̓�l���ᔽ�����Ă���ƔF�߂�Ƃ��́A��֎Ԃ��~�����A�Ƌ��̒�
�����߂邱�Ƃ��ł��܂��B
�����߂邱�Ƃ��ł��܂��B
�@��֎Ԃ̓�l���ᔽ�����鋰�ꂪ����Ƃ��́A�x�@���́A���H�ɂ������ʂ̊댯��h�~����
���ߕK�v�ȑ[�u���Ƃ邱�Ƃ��ł��܂��B
���ߕK�v�ȑ[�u���Ƃ邱�Ƃ��ł��܂��B
�����P�W�N�U���{�s
����@���ԑ�
�P�@��@���ԂŁA�^�]�҂̐ӔC�Njy���ł��Ȃ��ꍇ�ɂ����āA�g�p�ҁi�Ԍ��ɋL�ڂ���Ă��鎩
���Ԃ̎�����j�ɑ��ĕ��u�ᔽ���̔[�t���������܂��B
���Ԃ̎�����j�ɑ��ĕ��u�ᔽ���̔[�t���������܂��B
�Q�@���u�ԗ��̊m�F�y�ѕW�͂̎�t�Ɋւ��鎖�����ԂɈϑ����邱�Ƃ��ł��邱�ƂƂȂ��
���B
���B
�����P�X�N�U���{�s
�����^�����ԁE���^�Ƌ��̐V��
�@�����Ԃ̎�ނƂ��ĐV�������^���������݂����A���^�����Ԃ��^�]���悤�Ƃ�����͒��^�Ƌ�
���Ȃ���Ȃ�܂���B�܂��A�Ή����钆�^����Ƌ��A���^���Ƌ����V�݂���܂��B
���Ȃ���Ȃ�܂���B�܂��A�Ή����钆�^����Ƌ��A���^���Ƌ����V�݂���܂��B
| |
|
|
| |
|
�@�Q�O�Έȏ�A�o���Q�N�ȏ� �i���ɑ傫�Ȏԗ��ł́A �@�Q�P�Έȏ�A�o���R�N�ȏ�j |
| |
|
�@�W�g���ȏ� �i�P�P�g���ȏ�j |
| |
|
�@�T�g���ȏ� �i�U�D�T�g���ȏ�j |
| |
|
�@�P�P�l�ȏ� �i�R�O�l�ȏ�j |
| |
|
|
|
| |
|
�Q�O�Έȏ�A�o���Q�N�ȏ� | �Q�P�Έȏ�A�o���R�N�ȏ� |
| |
|
�T�g���ȏ�P�P�g������ | �P�P�g���ȏ� |
| |
|
�R�g���ȏ�U�D�T�g������ | �U�D�T�g���ȏ� |
| |
|
�P�P�l�ȏ�Q�X�l�ȉ� | �R�O�l�ȏ� |
�@��^�Ƌ��A���^�Ƌ��y�ђ��^����Ƌ��́A�H�㎎���y�ю擾���u�K�����{����܂��B
�@���^����Ƌ��́A�Q�P�Έȏ�łR�N�ȏ�̌o����L������łȂ���Ύł��܂���B
�@�����O�ɕ��ʖƋ����Ă�����́A��������ȑO�͈̔́i�ԗ����d�ʂ��W�g�������A�ő�ύ�
�ʂ��T�g�������̒��^�����ԁj���^�]���邱�Ƃ��ł��܂��B
�ʂ��T�g�������̒��^�����ԁj���^�]���邱�Ƃ��ł��܂��B
�����P�X�N�X���P�X���`
�{�l�m�F���ނ̒�
�^�]�Ƌ��i���Ƌ����܂ށB�j�̐\���ɓ������āA�Y�t���͒��邱�ƂƂ���Ă���Z���[�̎ʂ�
���ɉ����A���N�ی��̔�ی��ҏA�Z����{�䒠�J�[�h�A�������̑��̏��ނŖƋ��\���҂��{�l��
���邱�Ƃ��m�F����ɑ������̂���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƂȂ�܂����i�{�ߑ�17���2����
7���j�B
���ɉ����A���N�ی��̔�ی��ҏA�Z����{�䒠�J�[�h�A�������̑��̏��ނŖƋ��\���҂��{�l��
���邱�Ƃ��m�F����ɑ������̂���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƂȂ�܂����i�{�ߑ�17���2����
7���j�B
�@�����P�S�N�U���P���̓��H��ʖ@�̈ꕔ�����̎�ȉ����_�ɂ��Ă̏Љ�����܂��B��
�����S�����x�@���̃z�[���y�[�W�Ŋm�F���Ă��������B
���Ƌ��̎擾�̊W
���Z���n�ȊO�Ō����ψ���̍s���Z�\����������悤�ɂȂ�܂����B(���ʈ��Ƌ���
��)
�@�Z���n�ȊO�̓s���{���ɂ���͏o���K���ŋ��K�������́A�����������̓s���{���̌����ψ�
��̋Z�\����������悤�ɂȂ�܂����B��̓I�ɂ́A���ǎ����ԋ��K���i�͏o���K���j�ł�
�Ƌ��̂��߂ɏZ���[���ڂ����Ɩ����A�Ƌ��������Ƃ������Ƃł��B
�@�������A���̏ꍇ�́A�Z�\�������i�̎��_�Łu�������i�ؖ����v���o����܂��̂ŁA���������
�Ď����̏Z���n�ł���s���{���ɂĊw�Ȏ��������A���i������̂܂ܖƋ������s�����A
�Ƃ������̂ł��B��ɋZ�\��������Ŋw�Ȏ����ƂȂ�܂��̂ŁA�������Q��邱�ƂɂȂ�A��
���ɂ������p�������Ȃ�܂��̂Œ��ӂ��Ă��������B
�����ʓ��Ƌ��E��^���Ƌ��̋Z�\���������H�ōs�Ȃ��邱�ƂɂȂ�܂����B
�@�]���͏���R�[�X�ł������Z�\�������A���H��ōs�Ȃ���悤�ɂȂ�܂��B�������A���H�ł�
���{���s�\�ȕ����ϊ��E�c�ԁE�s�p�R�[�X�Ȃǂ̈ꕔ�̉ۑ�ɂ��ẮA����R�[�X�ōs��
���܂��B
�@���H�͊������H������H�Ȃǂ��܂ނ����ނ˂U�L�����[�g���قǂ̃R�[�X�ŁA�w�肳�ꂽ�ꏊ
�ł̒�~�Ȃǂ̉ۑ肪����܂��B
�@�Ȃ��A�H�㎎�����s�Ȃ���͕̂��ʓ��Ƌ��Ƒ�^���Ƌ��݂̂ł��B���̑��̑���Ƌ���
�Z�\�����͏]���ǂ���A��������ōs�Ȃ��܂��B
�����ʓ��Ƌ��E��^���Ƌ��̎擾�ɂ͍u�K���`���t�����邱�ƂɂȂ�܂����B
�@���}�~�쏈�u�Ɋւ���u�K�i�U���ԁj�ƁA���q�����Ԃ̉^�]�Ɋւ���u�K�i�댯�\���^�]�R��
�ԁA��Ԃ∫�������ɂ�����^�]�Q���ԁA�g�̏�Q�ғ��̏�Ԏ��̉^�]�P���ԁj�̍��v12���Ԃ��`
���t���ƂȂ�܂����B
���Ƌ��̍X�V�W
����ʉ^�]�҂̖Ƌ��̗L���������]���̂R�N����T�N�ɉ����ɂȂ�܂��B
�@�]���͗D�lj^�]�ҁi�S�[���h�Ƌ��j�݂̂��L�������T�N�������̂��A��ʉ^�]�ҁi�ߋ��T�N�Ԃ�
�ᔽ�����y���ᔽ�i�R�_�ȉ��̈ᔽ�j�P��݂̂̕��j���T�N�ƂȂ�܂��B�������A�ߋ��T�N�Ԃɐl
�g���̂��N���������A���S�^�]�҂�Ƌ������T�N�����̕��A����^�]�ҁi70�Έȏ�j�͓K�p�����
����B
���a�C��C�O���s�ŖƋ����������Ă��p�����čĎ擾�ł��܂��B
�@��ނȂ����R�ɂ��Ƌ��̍X�V�����A�����ƂȂ����ꍇ���U�����ȓ��ɍĎ擾������
���́A����܂ł̖Ƌ����p���������̂Ƃ��Ď��܂��B�D�lj^�]�ҁi�S�[���h�Ƌ��j�Ȃǂ�
���̂܂��ł��B
������ҍu�K�̎�u�Ώ۔N�70�Έȏ�ɂȂ�܂��B
�@����ҍu�K�ɂ�鎖�̌������ʂ��������Ƃ�A���㑝����ł��낤����҂̌�ʎ��̂����炷��
�I�ŁA��u�Ώ۔N��]����75�Έȏォ��A70�Έȏ��Ɉ����������܂��B
���X�V���u�K�̎�ނ������܂��B
�@���ߍׂ����u�K���e�ɑΉ����邽�߂ɁA�ȉ��̂悤�ɍu�K�̎�ނƓ��e�������܂��B
�@�@�D�lj^�]�ҍu�K�i��30���j
�@�@�@�T�N�Ԃ̉^�]�o���Ƃ��̊Ԃ̖����̖��ᔽ�̕�
�@�A��ʉ^�]�ҍu�K�i��P���ԁj
�@�@�@�T�N�Ԃ̉^�]�o���҂ŁA�ߋ��T�N�ȓ��Ɍy���Ȉᔽ�i�R�_�ȉ��j���P��݂̂̕�
�@�B�ᔽ�^�]�ҍu�K�i��Q���ԁj
�@�@�@�D�lj^�]�ҁA��ʉ^�]�ҁA����X�V�҈ȊO�̕�
�@�C����X�V�ҍu�K�i��Q���ԁj
�@�@�@�V�K�Ƌ��擾��T�N�����̎҂ŁA�y���Ȉᔽ���P��ȉ��̕�
�@�@�@����L�̍u�K�̎�ޑ����ɔ����A�����ł͊e�u�K�Z���^�[�̎�t�j���E���ԓ����ύX��
�@�@�@�@�Ȃ�܂����B�X�V���߂Â��Ă�����́A�������ψ���瑗�t�����Ƌ��؍X�V�̂�
�@�@�@�@�m�点�̃n�K�L���m�F���Ă��������B
�@�e�u�K�Z���^�[�̍Č�t��t���Ԃ��A�����̌ߌ�Q������ߌ�Q���R�O���܂ł̊��ƂȂ�܂�
���B�Ȃ��A�e�x�@���ł̎�t���Ԃ͏]���ʂ�A�����̌ߑO�W��30������ߌ�T���܂ł̊Ԃł��B
���Ƌ��̍X�V���Ԃ��P������������܂��B
�@�X�V�ł�����Ԃ��A�a�����P�����O�����a�����̂P�������܂ł����v�Q�������ɂȂ�܂����B��
�����A�{�N�Ɍ���A�V���P���ȍ~�̒a�����̕������ΏۂɂȂ�܂���I
�i��j�@�a�����@�@�X�V����
�@�@�@�U��30���i���j�@�@�T��30���i�j�`�V���P���i���j
�@�@�@�V���P���i���j�@�@�U���P���i�y�j�`�W���P���i�j
�@�@�@�V��30���i�j�@�@�U��30���i���j�`�W��30���i���j
�@�@�@���L�����Ԃ̖������A�y�E���E�Փ��̏ꍇ�́A���̗������������ɂȂ�܂��B
���D�lj^�]�҂͏Z���n�ȊO�̓s���{���ŖƋ��̍X�V���ł��܂��B
�@�������A�X�V���Ԃ̑O���̂P�������i�a�����̂P�����O����a�����̓����܂Łj�Ɍ���܂��B
�@��̓I�Ȑ\�����@�ɂ��ẮA���ꂼ��̓s���{���x�@�ɂ�����o�R�\�������ݒu�\��ꏊ�i�x
�@���z�[���y�[�W�ɂ���܂��j����Q�Ƃ��������B
�������^�]�ґ�W
���𐌂��^�]���̈����E�댯�ȉ^�]�������҂ɑ��锱�����������Ȃ�܂����B
�i��j�@�@�@�i�����O�j�i������j
�@�@�𐌂��^�]�@�@15�_�@���@25�_
�@�@���Ƌ��^�]�@�@12�_�@���@19�_
�@�@���C�тщ^�]�@�U�_�@���@13�_�@�i�ċC���̃A���R�[���Z�x��0.25mg/l�ȏ�̏ꍇ�j
�@���̑��̔����W�̉����_�͌x�@���̃z�[���y�[�W���������������B
����Q�ғ��̌��i���R�̌������W
�����̕a�C���ɂ������Ă�����͖Ƌ������Ȃ��A�Ƃ������i���R���p�~�ɂȂ�܂����B
�@���i���R�̔p�~�ɂƂ��Ȃ��A�����Ԃ̉^�]�Ɏx�Ⴊ���邩�ǂ������ʂɔ��f�������ƂɂȂ��
�����B��̓I�ɂ́A�����ɍ��i���Ă��A���̕a�C�ɂ������Ă��ĉ^�]�Ɏx�Ⴊ����ꍇ�ɂ��Ƌ�
�̋��ۂ��Ȃ����ꍇ������܂��B�܂��A���łɖƋ����擾���Ă�����ɑ��ẮA�Ƌ��̎���
�����~���Ȃ����ꍇ������܂��B
�@�ΏۂƂȂ�a�C�͈ȉ��̒ʂ�ł��B
�@���_����ǁi���S�ȉ^�]�ɕK�v�Ȕ\�͂������Ǐ��悵�Ȃ����̂������j
�A�Ă�i����̂�����̖����A���삪�ӎ��^����Q�ɂȂ�Ȃ��A���삪�������݂̂ł������
�������j
�B�Ĕ����̎��_�i�]�S�̂̋����ɂ�莸�_����a�C�ŁA����Ĕ��̂�����̂�����̂������j
�C�����o���̒ጌ���ǁi�l�דI�Ɍ����߂��邱�Ƃ��ł�����̂������j
�D�������a�i�����a�E���a���܂݁A���S�ȉ^�]�ɕK�v�Ȕ\�͂������Ǐ��悵�Ȃ����̂���
���j
�E�d�x�̖��C�̏Ǐ��悷�鐇����Q
�F���̑��A���S�ȉ^�]�ɕK�v�Ȕ\�͂������Ǐ��悷��a�C
�@�܂��A�����̂��̂̂ق��A���̂��̂��Ƌ��̎������E��~�̑Ώ��ƂȂ�܂��B
�@�s��
�A�ȉ��̐g�̂̏�Q
�@(1)�ڂ������Ȃ�����
�@(2)�̊��̋@�\�ɏ�Q�������č��������Ă��邱�Ƃ��ł��Ȃ�����
�@(3)�l���̑S�������������̂܂��͎l���̗p��S�p��������
�@(4)���̑��A���S�ȉ^�]�ɕK�v�ȔF�m�E����̂����ꂩ�̔\�͂��������ƂƂȂ����
�i�@��91���̋K��ɂ�������t���A���͂����ύX���邱�Ƃɂ��A���̔\�͂����邱�Ƃ�
���炩�ł�����̂������j
���Ƌ��\�����A�X�V�\�����ɏǏ̐\��������悤�ɂȂ�܂����B
�@��̓I�ɂ́A�\�����Ɉȉ��̍��ڂɂ��ċL�����闓���V�݂���܂����B���̍��ڂɊY������
���A���S�ȉ^�]�Ɏx�Ⴊ����Ǝv������ɑ��ẮA�a�ɂ��ċ�̓I�ɂ��b���f�����Ƃ�
�Ȃ�܂��B
�E�a�C�������Ƃ��āA���͌����͖��炩�łȂ����A�ӎ������������Ƃ������
�E�a�C�������Ƃ��Ĕ���I�ɐg�̂̑S�����͈ꕔ�̂������܂��͖�Ⴢ��N���������Ƃ������
�E�\���Ȑ������Ԃ�����Ă���̂ɁA�����������Ă���Œ����荞��ł��܂����Ƃ��T�R��ȏ゠
���
�E�a�C�𗝗R�Ƃ��āA��t����Ƌ��̎擾���͉^�]���T����悤�������Ă����
�����̕a�C�ɂ������Ă���\���̂�����ɂ͗Վ��K���������s�Ȃ��ꍇ������܂��B
�@�Ƌ����擾���Ă�����A�����ɍ��i���������Վ��K�������̒ʒm�����ꍇ�ɂ́A�Ƌ��ۗ̕�
�ƂȂ�܂��B���̗Վ��K���������Ȃ����͖Ƌ��̎��������~�ƂȂ�܂��B
�@���ꂩ��Ƌ����擾���悤�ƍl���Ă�����́A�Ȃ�ׂ��Ƌ��\���⋳�K���ւ̓����̑O
�ɁA�^�]�K�����k���s�Ȃ��Ă��������I
�@�@�A����@�F�@���x�@�{���^�]�Ƌ��ہ@�^�]�K�����k����
�@�@�@�@�@�@�@�@��502-0003
�@�@�@�@�@�@�@�@�s�O�c�����P����22�ԂW��
�@�@�@�@�@�@�@�@TEL�@�O�T�W-�Q�R�V-�R�R�R�P�i��j
�@�@��t���ԁF�@���j������ؗj���i�j�Փ��������܂��j�@�ߌ�P�F�O�O�`�S�F�O�O
�����̑�
���g�̏�Q�ҕW������������܂��B
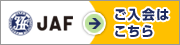
�@���̕s���R�ł��邱�Ƃ𗝗R�ɖƋ��ɏ�����t����Ă���^�]�҂́A���ʎ����Ԃ��^�]����ꍇ
�ɉe�����y�ڂ�������̂���Ƃ��ɂ́u�g�̏�Q�ҕW���v��\������悤�w�߂邱�ƂƂȂ�܂�
���B
�@���̕W���̂���Ԃɂ́A���̎Ԃ͕��⊄�荞�݂Ȃǂ��֎~����܂��B
���Ƌ���Ԕ[���Ă���]�҂ɂ͖Ƌ��T�C�Y�̉^�]�o���ؖ��������s����܂��B
�@����Ȃǂ𗝗R�ɖƋ���Ԕ[�i�w��������j�����ꍇ�A�]���͎茳�ɖƋ����c���Ă�����
�Ƃ͂ł��܂���ł����B����A��]�҂ɂ͖Ƌ���Ԕ[���Ă���P�����̊ԂɁu�^�]�o���ؖ�
���v�Ƃ����A�Ƌ��ؓ����T�C�Y�E�����f�U�C���̏ؖ����̔��s��\���ł���悤�ɂȂ�܂����B��
��́A�����ɂ͉^�]�o���ؖ����Ƒ傫��������Ă���A�����E���N�����E�Z���E��t�N�����͋L��
����܂����A�{�ЁE�L�������E�Ƌ��ؔԍ��͋L�ڂ���܂���B��ʐ^���V���Ɏ�蒼���ō쐬����
�܂��B
|

